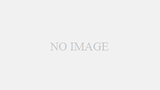オペレーショナル・リスク(以下、オペリスク)は、金融機関の収益や資本に対して重大な影響を及ぼす可能性があります。バーゼル銀行監督委員会がオペリスクを定義し、計測・管理を求めている背景には、過去に発生した巨額損失事例が存在します。システム障害、取引ミス、法令違反、コンプライアンス不備など、オペリスクは金融機関の信頼性を根底から揺るがすものです。
1. 規制上の位置付け
バーゼル規制において、オペリスクは信用リスク、マーケットリスクと並ぶ「主要なリスクカテゴリー」として位置付けられています。バーゼルIIでは新たに枠組みに組み込まれ、自己資本比率算出においてオペリスクに対応する資本保持が求められるようになりました。バーゼルIII以降もその重要性は維持され、内部管理態勢やストレステストとの関連でも重視されています。
2. コンダクトリスクとの関係
オペリスクの定義には、従業員の不適切な行為や法令違反に伴う罰金・訴訟・補償損失も含まれます。これらは一般に「コンダクトリスク」と呼ばれ、近年ますます重要視されています。例えば、不正な金融商品の販売や利益相反管理の不備によって顧客に損害を与えた場合、そのコストはオペリスクとして資本規制上も捉えられる対象となります。各国監督当局もコンダクトリスクを独立したリスク領域として監視強化しており、実務上はオペリスク管理の枠組みの中で統合的に扱うことが求められます。
3. 実務におけるオペリスクの影響
オペリスクは金融機関の健全性を揺るがすだけでなく、レピュテーションリスク(評判リスク)を通じて顧客離れや市場での信用低下を引き起こします。特に近年は、ITシステムの高度化やサイバー攻撃の脅威増大に伴い、加えてコンダクトリスクを巡る規制圧力の高まりから、オペリスクの管理はかつてないほど重要性を増しています。
4. 規制対応と内部統制
金融機関は、オペリスクを識別・評価し、損失データベースの整備や自己評価(CSA: Control Self Assessment)を通じて、管理態勢を強化することが求められています。また、内部監査部門の独立性確保や、経営層への定期的な報告体制も規制上重視されます。コンダクトリスクを含む幅広いオペリスクの管理が、内部統制の成熟度を示す一つの指標となっています。
5. まとめ
オペリスクは「発生確率は低いが、一度発生すると巨額損失につながる」特性を持ちます。その中でも、コンダクトリスクは顧客保護や市場の公正性に直結するため、特に厳格な管理が求められています。単なる規制対応ではなく、経営戦略の一部としてリスク管理を組み込むことが不可欠であり、オペリスク管理は金融機関が持続的に信頼を維持するための基盤といえるでしょう。