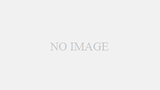市場リスク(Market Risk)は、金利、為替、株価、商品価格などの市場変数の変動によって金融機関が損失を被る可能性のあるリスクを指します。
金融取引のグローバル化・高速化に伴い、市場リスクは金融機関の健全性を左右する重要なリスクカテゴリーの一つとして、信用リスクやオペレーショナル・リスクと並びバーゼル規制の柱に位置付けられています。
1. 市場リスクの定義と範囲
バーゼル銀行監督委員会(BCBS)は、市場リスクを次のように定義しています。
“The risk of losses in on- and off-balance sheet positions arising from movements in market prices.”
(市場価格の変動により、オンバランスおよびオフバランスのポジションに損失が生じるリスク)
市場リスクには、主に以下の要素が含まれます。
- 金利リスク(Interest Rate Risk):債券価格や金利スワップ価値の変動による損益変動
- 為替リスク(FX Risk):通貨レートの変動による外貨建取引・ポジションの評価損益
- 株価リスク(Equity Risk):株式・株価指数先物などの価格変動に伴うリスク
- 商品リスク(Commodity Risk):原油・金属などの商品価格の変動に起因するリスク
- クレジット・スプレッド・リスク(CSR):債券等の信用スプレッド変動による評価損益の変動
これらの市場変数は相互に関連しており、複合的に金融商品の価値を変動させます。
2. トレーディング勘定とバンキング勘定の区分
市場リスクが資本規制上問題となるのは、主に「トレーディング勘定(Trading Book)」に属するポジションです。
トレーディング勘定とは、短期的な売買益を目的として保有する金融商品(債券・株式・デリバティブなど)を指します。一方、「バンキング勘定(Banking Book)」には、長期保有を前提とした貸出債権や預金などが含まれます。
この区分は、自己資本比率計算におけるリスク加重資産(RWA)の区分に直結するため極めて重要です。
ただし、近年の金融商品の複雑化に伴い、この境界の曖昧さが問題視され、後述するFRTB(Fundamental Review of the Trading Book)で明確化が進められました。
3. 市場リスクの規制上の位置付けと進化
市場リスクは、バーゼル規制の枠組みの中で段階的に整備されてきました。
- 1996年市場リスク修正(Market Risk Amendment)
初めて市場リスクに対して自己資本要件が導入され、VaR(Value at Risk)による内部モデルの使用が認められました。 - バーゼルII(2004年)
信用リスク・オペリスクと並ぶ主要リスクとして体系化され、内部モデル手法(IMA)と標準的手法(SA)が確立しました。 - バーゼル2.5(2011年)
リーマン・ショック後の教訓を踏まえ、ストレスVaRやIRC(Incremental Risk Charge)などの補完的指標を導入。 - バーゼルIII最終化/FRTB(2019年)
VaRの限界を克服するため、Expected Shortfall(ES)を採用。
また、トレーディング勘定とバンキング勘定の境界再定義や、モデルの粒度向上が進められました。
4. 市場リスクの重要性と近年の傾向
近年は、金利上昇局面、地政学リスク、流動性の枯渇といった要因により、市場リスク管理の難易度が増しています。
特に、金利リスクやクレジット・スプレッドの変動が、銀行の評価損益や自己資本に直接影響を与える事例が増加しています。
また、非線形リスク(オプション取引など)やクロスリスク(為替×金利など)の管理も複雑化しています。
5. まとめ
市場リスクは、金融機関のポートフォリオ全体の健全性を左右する中核的なリスク要因です。
規制面ではFRTBを通じて精緻化が進む一方、実務的にはモデルの複雑化・データ要件の高度化が進み、経営資源の投入が不可欠となっています。
市場リスク管理は、もはやトレーディング部門だけの課題ではなく、経営レベルのリスク戦略として位置付ける必要があります。