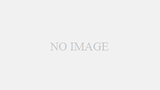1. VaR登場の背景
1990年代初頭、金融市場のボラティリティが急拡大する中で、金融機関はポートフォリオ全体のリスク量を定量的に把握する手法を求めていました。こうした状況で登場したのがVaR(Value at Risk)です。JPモルガンが1994年に公表した「RiskMetrics」は、一定期間・一定の信頼水準における最大損失額を算出するというシンプルな概念を示し、リスク管理の標準指標として急速に普及しました。
監督当局もこの動きを受け、1996年の「市場リスク修正(Market Risk Amendment)」において、VaRを内部モデルとして資本計測に使用することを認めました。これにより、市場リスク管理の実務と規制が大きく転換点を迎えることになります。
2. バーゼルIIにおける市場リスク管理の枠組み
バーゼルIIでは、市場リスクの資本要件を算出するための2つの手法が併存していました。
- 標準的手法(Standardised Approach; SA):監督当局が定めたリスクウェイトに基づいて資本を算出する方法。
- 内部モデル手法(Internal Models Approach; IMA):金融機関が自ら構築したVaRモデルを用い、当局の承認を得た上で資本を算出する方法。
内部モデル手法を採用するには、過去1年間の市場データを基にした99%信頼水準・10日保有期間のVaRを算出する必要がありました。さらに、バックテスティングによってモデルの妥当性を検証し、当局による定期的なレビューを受けることが求められました。
この枠組みは、リスクの「内部モデル化」を規制が正式に認めた初の事例であり、各行のリスク管理手法の高度化を促進しました。
3. VaRの理論的基礎と実務上の課題
VaRの基本的な定義は「一定の信頼水準で、一定期間内に発生し得る最大損失額」です。たとえば、99%信頼水準・1日VaRが1億円であれば、「1日のうち99%の確率で損失は1億円を超えない」と解釈されます。
VaRには以下のような算出方法があります:
- 分散・共分散法(Parametric VaR):正規分布を仮定し、平均と分散から算出する。
- ヒストリカル法(Historical Simulation):過去データの実績値を再現してシミュレーションする。
- モンテカルロ法(Monte Carlo Simulation):確率的モデルを用いて多数のシナリオを生成し、損失分布を推定する。
しかし、実務面では次のような課題が指摘されてきました:
- 正規分布仮定に基づくため、極端な市場変動(テールリスク)を過小評価する。
- 市場が平穏な期間のデータに依存しやすく、「平時バイアス」が生じる。
- オプションや構造的商品のような非線形リスクを十分に捉えられない。
4. リーマン・ショックが示したVaRの限界
2008年のリーマン・ショックでは、市場の変動がかつてない規模で拡大し、VaRモデルが想定する範囲を大きく超える損失が発生しました。これにより、VaRが実際のリスクを反映できないという問題が顕在化しました。
この反省から、バーゼル2.5(2011年)では以下のような補完的措置が導入されました:
- ストレスVaR(Stressed VaR):過去のストレス期間のデータを用いたVaRを追加計測。
- IRC(Incremental Risk Charge):債券ポートフォリオの信用イベントによる損失リスクを補足。
- CRM(Comprehensive Risk Measure):複雑なトレーディングポジション(特にコリレーショントレーディング)への対応。
監督当局は、「VaRはリスクを説明する指標ではあっても、予測する指標ではない」と明言し、次世代のリスク計測モデルの必要性が認識されました。
5. まとめ
VaRは、リスク管理の定量化を可能にした画期的な手法であり、金融機関におけるリスク文化の形成に大きく貢献しました。しかし、同時にその前提や限界も明確になり、リーマン・ショック以降は「過信の危険」を象徴する概念ともなりました。
この反省を踏まえ、バーゼル委員会は市場リスク枠組みを抜本的に見直し、**Expected Shortfall(ES)を中心とする新しい枠組み、すなわちFRTB(Fundamental Review of the Trading Book)**を導入しました。