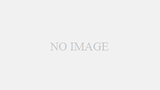1. CVA(信用評価調整)とは?——信用リスクの新たな視点
CVA(Credit Valuation Adjustment)とは、デリバティブ取引に内在する相手先の信用リスクを反映した時価調整額のことです。
通常の時価評価(フェアバリュー)は市場価格に基づきますが、CVAは相手方の信用リスクを考慮した調整額であり、損失の可能性を評価するものです。
■ なぜ重要か?
- リーマン・ショック後、多数のデリバティブ取引で信用リスク損失が顕在化
- デリバティブ取引では、与信額が市場価格により変動するため、従来の信用リスク管理だけでは不十分
- 国際的にCVAリスクを自己資本比率の算定対象とする動きが進展
2. CVAリスクの発生メカニズム
CVAリスクは、以下の2つの要素から発生します:
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 市場リスク | 金利・為替・株価等の変動により、デリバティブの時価が動くこと |
| 信用リスク | 相手先の信用力低下により、与信先のデフォルト確率が上昇すること |
■ CVAリスクの特徴
- 市場リスクと信用リスクの融合領域
- 取引相手がデフォルトしなくても、CVAの変動により損益が発生する点が特徴的
3. バーゼル規制におけるCVAリスクの位置付け
■ 自己資本比率への影響
バーゼル規制では、CVAリスクを市場リスク・信用リスクとは独立したリスクカテゴリーとして自己資本比率に反映することが義務付けられています。
■ バーゼルⅢ最終化の動向
- CVAリスクの計測手法をBA-CVAとSA-CVAの2種類に統一
- 従来の計算方法(標準的リスク計測方式・先進的リスク計測方式)は廃止
- 日本でもバーゼルⅢ最終化に伴いすでに適用済み(多くの銀行がBA-CVAを選択)
4. 日本の現行規制とCVAリスクの実務的影響
■ 日本における状況
- デリバティブ市場の規模が欧米に比べ相対的に小さいことから、BA-CVAを採用する銀行が大半(現状SA-CVAを採用しているのはMUFGとみずほの2行のみ)
- 日本においては、BA-CVA・SA-CVAに代わる簡便法も許容
- 一部の大手行ではSA-CVAの検討も進むが、データ要件の厳しさが課題
■ 実務への影響
- デリバティブ取引全体にわたる信用リスク管理体制の強化が不可欠
- CVAリスクヘッジの精緻化、内部資本配賦の高度化が今後の焦点
✅ まとめ
CVAリスクは、デリバティブ取引に伴う新たな信用リスク管理の中心的テーマであり、バーゼル規制上も資本比率計算に不可欠な要素となっています。
日本では、まずBA-CVAの適切な実務運用を徹底することが現実的な対応方針となるでしょう。