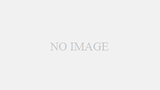1. 購入債権とは何か?
IRB方式における購入債権向けエクスポージャーとは、銀行が第三者から**譲受する債権(売掛債権等)**を指し、売却者(セラー)を通じて間接的に信用リスクを引き受ける取引です。
代表的な例には、ファクタリングや企業間債権の流動化があります。
2. アセットクラス分類と評価アプローチ
購入債権は、以下のように与信先の性質に応じて2つのアセットクラスに分類されます。
| 区分 | 概要 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 購入事業法人等向け債権 | 法人や政府関連等が債務者 | 原則としてIRB評価を準用 |
| 購入リテール向け債権 | 小口消費者が債務者 | 属性の均一なプール単位での評価 |
3. 適用手法とパラメータ推計の原則
購入債権においても、原則はIRB方式を踏襲しますが、FIRBとAIRBの区分に応じた評価が求められます。
❗️「すべて推計」ではない
- 大企業などFIRB対象の購入事業法人等向け債権では、PDのみを自行推計し、LGDおよびEADは当局指定値(定められた係数)を用いる。
- AIRB対象(例:中堅・中小企業等)や購入リテール向けでは、PD・LGD・EADすべてを自行推計する必要があります。
4. ダイリューションリスクへの対応
購入債権特有の論点として、ダイリューションリスク(債権希薄化リスク)が存在します。
これは債務者の信用状況とは関係なく、以下の要因により債権価値が低下するリスクです。
- 商品の返品やキャンセル
- 割引・値引き交渉
- 債務免除などの契約修正
✅ RWA(リスク・アセット)評価方法
IRB方式では、ダイリューションリスクに係る期待損失を次の通り算定します:
- PD:希薄化による期待損失率
- LGD:100%
- マチュリティ:1年固定
この値をもって、通常のRW計算式に代入してリスク・ウェイトを求めます。
⚠ 実務上の対応
- 希薄化に関する期待損失率は実績データが乏しく、推計が極めて難しいのが現実
- 多くのケースで、売却者(セラー)にダイリューションリスクを保証させる契約を締結
- 保証契約により、RWAの算定対象外または軽減対象とすることが可能
5. 管理上の留意点
| 論点 | 対応策 |
|---|---|
| 情報の非対称性(譲渡元依存) | 契約でデータ提供義務を明確化 |
| 保証条件の把握 | ダイリューション補償の有無を記録管理 |
| 複数債権者の識別管理 | 与信先別管理台帳の整備 |
✅ まとめ
購入債権向けエクスポージャーは、IRB方式の下でも一律にパラメータを推計する必要はなく、対象先の区分(FIRB/AIRB)によって評価方法が異なります。
また、ダイリューションリスクは、独自の評価ロジック(PD:期待損失、LGD:100%、マチュリティ:1年)が設定されていますが、この推計は困難であり、実務上は保証契約で対応するのが一般的です。